366日ドラマネタバレ1話ネタバレ
音楽教室の事務受付をしている雪平明日香は高校の同窓会で同級生の水野遙斗と再開する。明日香は高校時代、遙斗のことが好きだったが、卒業式の時に他の女子生徒から花を渡されていることを目撃してしまう。他の男子たちに二人でいるところを「カップル誕生か!?」と揶揄われているところを「遙斗とはそんなんじゃないから!ありえないから!」と強く否定してしまう。この言葉で、実は明日香のことが好きだった遙斗もショックを受けてしまい、お互い勘違いして思いを伝えられないまま高校を卒業し、それきり疎遠になってしまっていた。同窓会の後に、遙斗の両親が営むお好み焼き屋に集まることになった明日香と遙斗、友人の下田莉子、小川智也。そこで互いの近況を報告し合い、明日香と遙斗も連絡先を交換しあった。その後、毎日連絡が来てないか気にしているが、互いに連絡しない日々が続く。そんな中、明日香が音楽教室の生徒である静原吾朗と一緒にいるところを遙斗が偶然目撃してしまう。明日香に桜の花びらがついているのを吾朗がとってあげているところを見て、付き合っている男がいると勘違いしてしまう。明日香は莉子から劇団員をやっている鮫島健司の公演に誘われる。鮫島もまた、高校時代の同級生であった。「行こうかな」と明日香も了承する。当時、莉子が急に公演に行けなくなってしまったのだが、そこには偶然にも遙斗が来ていた。隣同士に座る二人。公演後、遙斗は明日香を食事に誘った。話が弾む二人。帰り道も思い出話に花が咲く。そこで明日香は「自分が東京の大学を受けたのは遙斗も東京に行くと思ったからだ」と告白する。「卒業式の日、ちゃんと気持ち伝えようと思っていた」と。遙斗は「あの花束は預かっただけ」と泣きそうになりながら伝える。そして遙斗は「俺たち、ここから初めてみない?」と提案する。二人は互いが高校の頃からずっと両思いであったことを初めて認識し、その日はずっと話をした。東京タワーに行ったことがないという明日香を「今度行こう」と遙斗はデートに誘う。そして、そのデートの日、明日香は待ち合わせ場所で遙斗を待っていた。そこへ急ぐ遙斗。明日香を見かけたが、そこに野球少年が通りかかる。少女の風船が木に引っかかっており、それをその少年が取ってあげようとしていた。明日香の姿が見えて、遙斗はそちらへ行こうとするが、その少年の姿が木になって振り返る。次の瞬間、少年はバランスを崩して、高い塀から落ちてしまいそうになった。そこを遙斗が駆けつけて、少年を助けるも、自分が代わりに落下してしまう。救急車で運ばれていく遙斗。待ち合わせ場所でずっと待っていた明日香。遙斗がなかなか来ないのだが、その時電話が鳴り、誰かからの通話を受けてどこかへ駆け出した。
366日ドラマネタバレ2話ネタバレ
遥斗の前で、懺悔する明日香
高校2年の時に、広島から転校してきて知り合って好きだった遥斗に、やっと再会してデートの約束をしたのに、突然に事故で入院し、右半身まひ、意識不明になり手術を受けます。主治医の池澤が手術で硬膜下血腫を除いたものの、数%の確率で意識が戻らないと宣告します。
池澤医師の息子は、明日香の音楽教室の生徒でした。明日香が遥斗の両親、遥斗の妹、花音に遥斗と待ち合わせをしていたと打ち明け、自分が約束なんかしなければよかったと後悔します。遥斗の両親は明日香のせいではないと、かばいます。
ナースの紗衣がICUに導くと、遥斗に全身痙攣が起きて、皆が動揺しますが、池澤が薬剤で抑えます。
感想:おもいやりのある遥斗が、少年の為に木に登って転落した運命は皮肉です。予期しない明日香にとっての試練です。
明日香に訪れたチャンス
明日香の高校時代の同級の、小川は明日香に自分が彼女だと遥斗の親に言わないのかと促しますが、明日香は言わないと答えます。
音楽教室に来た静原が、浮かない顔の明日香に何かあったのかと心配しますが、明日香は語りません。
すると、明日香の上司が明日香にクラリネットの講師にならないかと提案します。受付事務だけの明日香にとってはチャンスです。明日香は戸惑います。
感想:クラリネットの講師という明日香のチャンスにかけるか、遥斗の見舞いを優先するか、迷うのは当然です。そんな明日香に声をかける明るい静原が、明日香の心の救いになる予感がします。
明日香の回想
明日香は病院に行くとICUに遥斗がいなくなっていて焦りますが、一般病棟に移っていて安心します。
すると、遥斗が木の枝に引っかかった風船を取ろうとして転落したのですが、その風船をとろうとした子供の親である、両親が遥斗の両親に謝罪に来ましたがが、遥斗の両親はなだめます。
明日香は眠る遥斗を見て高校時代に図書室で10分後に起こしてといわれ、起きた途端に、おはようと、ほほ笑んだ遥斗の顔を思い出します。
明日香がナースの紗衣に遥斗の意識が戻るのかと問いますが、自分にはわからないと答え、その様子を花音が見ていました。
感想:少年の両親が謝罪に来ても、責めることなく感情を押し殺す遥斗の両親が痛々しいです。
明日香の決断
明日香は莉子にクラリネットの研修を受けると夜に遥斗の見舞いにいけないので、受けないと決めます。
さらに、明日香は莉子から遥斗の見舞いにはいかないと断ると、莉子は明日香に遥斗の未来を背負っていく覚悟があるかと問います。クラリネットの講師になるチャンスを振ってしまう明日香に、自分たちは29歳で、将来を考える大事な時期だと諭します。一方、花音は、彼氏の竜也に、家族でない人まで遥斗を巻き込めないと言います。
その莉子から花音に連絡がきますが、2人は幼馴染で、遥斗も花音をかわいがっていました。
感想:クラリネットの講師の道も捨てた明日香の将来を心配する莉子の意見は納得できるものですが、明日香の動揺が、それだけ深いものだと思います。
絶望的な遥斗の運命*
遥斗は手術を受けて1ケ月が経過しますが、意識が戻りません。遥斗は術後1か月がたちます。花音は明日香に遥斗が、一生、意識が戻らないかも知れないと言われ、遥斗に、かかわらないで、こなくていいと断り、輝彦は明日香に気持ちの整理がつかないと言って、遥斗から遠ざけました。
明日香は驚いて見舞いを置いて病室をさります。
感想:遥斗の両親、花音に面会を断られた明日香には、苛酷な運命です。
吉幡と遥斗の関係
吉幡は小川から遥斗の事を聞きますが、見舞いに行きません。吉幡の妻は見舞いに行かないのかと促しますが、行きません。2016年、かつて、吉幡は遥斗に金に振り回せる人生なんかと言い合って喧嘩別れしました。
感想:吉幡と遥斗には仕事上のわだかまりがあるようで、気になります。吉幡は遙斗の姿を見れば気持ちが変わるかもしれません。
池澤の明日香への助言
明日香が池澤医師に会って、遥斗の様子を聞きますが、池澤は医者の立場でも何とも言えないと答え、明日香に見舞いに行かないのかと問います。
迷う明日香に、池澤は、どうするかより、どうしたらいのかと考えた方がいいとアドバイスします。
感想:池澤が迷う人生の選択より、自分の気持ちに忠実に生きた方が良いという意見が明日香の背中を押したのが、微笑ましいです。
決意を語る明日香
明日香は見舞いにいくと、花音と遥斗の両親がいて、明日香はここに来るのを許してもらえないか、遥斗と、事故の2日前、これから、ずっと、そばにいようと約束したと訴えます。
花音はまだ始まったばかりでしょ、遥斗が、もう眼を覚まさないかもしれないから、明日香の仕事のチャンスまで犠牲にしないでと忠告します。
しかし、明日香は、これからのことを考えて、わくわくしたと言いかえし、今は苦しいけれど、遥斗に会えてよかったと言います。
高校卒業時、明日香は斗が北海道に行くと聞いて駅に見送りに行ったが、遥斗が来なくて、すれちがいでした。10年たってやっと会えて、遥斗は遙斗だから、あきらめたくないと言います。それを聞いた輝彦はありがとうと感謝します。花音は遙斗が明日香に渡すはずのプレゼントを渡しました。明日香は花音をさそって遙斗のおすすめの鎌倉の桜のはちみつを一緒に味わいます。
明日香が明日香をみて病院の前から引き返そうとする木幡を見て、声をかけますが、吉幡は去ります。
感想:遥斗への強い思いを理解してくれた花音と両親には感動的です。花音と明日香が、心が通じて、はちみつの味をあじわう姿が、ホットする場面でした。
次回、明日香は莉子に病院付近で小幡を見かけたと言うと、莉子は吉幡と遥斗がいつも様子がおかしかったと言います。莉子が、おそらく2人のしこりを、ほぐしてくれそうです。
すると遥斗の会社の木嶋は遙斗の診断書を受け取り、遥斗が準備していた店の壁面に飾るアート作品にこだわっていたと聞いた明日香が探すようです。
366日ドラマネタバレ3話ネタバレ
高校の同級生だった明日香と遥斗。2人は高校時代に周りから見てもお似合いの2人でした。高校の卒業式の時にてっきり2人は付き合うのかと思われていましたが、遥斗が他の女の子から花束をもらうのを見てしまった明日香は勘違い。
てっきり遥斗がその子と付き合うと思ってしまい、クラスメートから遥斗と付き合うのかと聞かれた際に、異性として見たことはないとはっきり言ってしまいます。そのことがきっかけで2人は疎遠になりますが、高校の同窓会をきっかけに再会。急接近した2人は今までの心の溝を埋め、付き合うことになりました。夜明けまで語り尽くした2人は明日、デートをしようと分かれました。ついにデート当日となり、待ち合わせ場所のスカイツリー前で待つ明日香。しかし、待っても遥斗がなかなか現れません。おかしいなと思い、連絡を入れますが既読にすらならず、待つばかり。すると、救急搬送された先の病院から遥斗が意識不明だと伝えられます。病状の良くならない遥斗と付き合うべきか悩みますが、明日香は彼女でいる道を選びました。遥斗が東京で任された仕事は新しいお店の企画でした。その店にこっそり明日香を連れて行ってくれたので明日香もそのことを知っていました。しかし、植物状態の遥斗。休職することにはなりましたが、お店のオープンを遅らせるわけにはいきません。後輩が引き継いでお店の立ち上げに携わることになりました。しかし、壁画に悩んでしまいます。資料からヒントを得られず、とても気に入った壁画があることだけを知っていた後輩が明日香に尋ねてきました。すると、思い当たるメモが残されていました。No.3と書かれ、そこには昔いつも一緒にいた仲良し5人組のうちの1人である和樹の名刺があったのです。ある時から距離を置くようになり、疎遠になった和樹。遥斗がどうしても壁画にしたかったのは高校時代に和樹が受賞した写真でした。その題名がNo.3だったのです。実は和樹にとって遥斗が高校時代に楽しみをくれ、遥斗との忘れられない出会いの場がNo.3と書かれた桜の木の前でした。和樹は写真部でその思い出の桜の木を写真に撮り、コンクールに出展したところ見事、優秀賞を受賞。しかし、高校卒業後は父親から養育費の振り込みもなく、お金に困る母親の元、進学先も国立にするなど自由な選択もできない状況でした。大学に進み、高校の同窓会に参加すると未来の明るい仲間たちとの違いが浮き彫りに。和樹はそっと距離を置くことにするのですが、遥斗は和樹の様子にいち早く気づきます。構わないで欲しいと思う和樹をはなそうとしない遥斗を困らせようとお金を貸して欲しいと頼むと、遥斗は惜しげもなくアメリカにメジャーリーグを見に行くために貯めていたお金を渡そうとします。和樹をますます追い込んでしまい、和樹は遥斗にひどい言葉をあびせて別れます。8年の歳月が経ち、遥斗が和樹の職場へやってきました。新店舗の壁画に和樹の写真を飾りたいというのです。経済的に母を助けたかった和樹でしたが、大学時代に母が再婚。居場所を失っていた和樹は社会人になり、お金が全手だと思うようになっていました。しかし、変わらない遥斗にどう接して良いかわからず、写真がどこにあるかもわからないため冷たい態度に。明日香は遥斗の代わりに和樹に頼んで、駆けずり回って写真を探します。すると、ようやく高校の写真部の先生が持っていてくれたことが判明。新店舗に飾ることになりました。明日香は和樹に連絡して、新店舗に飾られた写真を見せます。すると、和樹のこころのわだかまりが解け、オープン日にはまたかつて仲の良かった明日香たちと一緒に集まることに。遥斗が目覚めてくれるのを待ち望む4人でした。

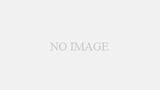
コメント